DE ROSA TITANIO Soloをフレームから組み立てる【ロードバイク組立記】シリーズ。
前回はフロントディレイラー(FD)の組み付けまで完了しました。
今回はリアディレイラー(RD)を組み付けて行きます。
準備するもの
焼き付き防止剤
トルクスレンチ
CAMPAGNOLO SUPER RECORD REAR DERAILLEUR (2015)
TITANIO SoloのコンポーネントはCampagnolo SUPER RECORDを組み付けます。コンポーネント一式、つまりGroupset(グループセット)は海外オンラインショップのMerlin Cycleから購入しました。
リアディレイラー(RD)の組み付けは付属の取扱説明書またはオフィシャルサイトを参照しながら行っていきます。
詳細はこちらにとてもわかりやすく丁寧に記載されているのでお任せするとして、FD組み付けに引き続き本エントリーでは余談を書いていきます(^^)
特徴 – その1
CampagnoloのCHORUS/RECORD/SUPER RECORDグレードのRDを見ると、Campagnoloのカーボン素材に対する探究心と技術力の高さがよくわかります。

有機的で複雑な曲面で構成された形状をカーボン素材で造形してしまうという、Campagnoloのこだわりというか執念のようなものを感じます。また、そうして出来上がったRDのデザインは本当に美しく、眺めているだけで幸せな気持ちになれます。
そして気持ちが軽くなるとRDも実際の重量以上に軽く感じ、いつもより速く走れるようになれます(^^) ※個人の感想ですが、大事なことです。
特徴 – その2
CHORUS/RECORDグレードとSUPER RECORDグレードの違いは軽量化のための肉抜き加工の数にあります。またチタンボルトを採用することでさらなる軽量化を図っています。そして、これらの積み重ねによりSUPER RECORDはRECORDに比べて”4g”だけ軽く仕上がっています。
ここで話は逸れますが、RDに限らず、SUPER RECORDを選ぶ理由としてRECORDより”4g”軽いという数値上の事実はあまり意味を持ちません。チタンボルトだから錆びないというのもメンテナンスにおいて多少有利に働きますが、それも副次的なメリットでしかありません。
SUPER RECORDを選ぶ理由は『Campagnoloが好きだから』、『SUPER RECORDの造形・デザイン(とデカール 笑)が好きだから』というシンプルな動機が多いのではないかと思っています。そして、自分のお気に入りのフレームにSUPER RECORDを組み付けて操れるというロマンにこそ、わずか”4g”という差や”コスパ”では計れない大きな価値があるように思います(^^)
DE ROSA TITANIO SoloへのRD組み付け下準備
さて、RDをTITANIO Soloのフレームへ取り付けようとしたところ、問題が発生しました。フレームのRDハンガーのネジ穴が微妙に小さくて、RDのネジが入らないのです。
ロードバイクフレームのタッピングについて
BBやRDハンガーのネジ穴はフレーム製造時に一応タッピング(ネジ切り)されていますが、それでも溝が浅かったりしてそのままではBBカップやRDが組み付けられない(ネジが入っていかない)ケースが普通にあります。
そこでショップで購入されたフレームの場合は、ショップが組み付け作業の一環として改めてタッピング(この場合はネジ山のさらい直し)をしてからパーツを組み付けしてくれているのです。さらに、しっかりしたショップであれば完成車でも一回全部バラして、タッピングやその他の下準備を施してから改めて丁寧に再組み立てしてくれます。
上記コラムのように、タッピングは大事な作業です。そしてBBのタッピングともなるとかなり大掛かりな作業となります。ちなみにBBタップ用の工具は結構なお値段がします(^^;)
TITANIO Soloは無塗装なので塗装によるネジ山つぶれは起こり得ないですが、もしもBBカップが入らなかったらショップにフレームを持ち込む覚悟もしていました。
幸い私のフレームはBBタップなしでカップが入ってくれたので、本当にホッとしました。
RDハンガーのタッピング工具
さて、RDハンガーのタッピングツールはそれほど高価でもなく、作業的にも個人レベルで可能な範囲なので自分でなんとかします。

購入したのは以下の2点です。注意点としては、ネジ山のピッチを間違えないこと。と言ってもカンパもシマノもRDハンガーのネジ山は共通なので、以下を準備すれば間違いないです。
タップハンドルは正直無くても作業できるかもしれません。ただし、タッピングで一番大事なのはネジ穴に対して綺麗に垂直に真っ直ぐタッピングすることです。ペンチなんかで掴んで回すと回転の中心がズレるので、個人的には今回のような一発勝負の時は安心代と割り切って購入して損はないと思いました。
ちなみに、このエントリーを書いてて初めて気が付きましたが、上の2点は前述のY’s Roadのコラムで使用しているタップツールと同じ組み合わせみたいですね(^^)
RDハンガーを自分でタッピングする
タップツールを写真のようにセットしてネジ山をさらい直します。

タッピングする時は焼きつき防止のために潤滑油を使用します。また切削する時に切削面に熱が発生しますが、熱は金属に負担を掛けるため、焦らずゆっくりと時間をかけて熱を逃がしながら作業します。
今回はチタン素材の切削なので、迷った挙句にいつもの焼き付き防止剤を潤滑油の代わりに使用しました。
また、タップツールを回す時のお約束は「1周回して半周戻す」の繰り返しですが、チタン素材は熱伝導率が低い(熱が逃げにくい)のでさらに慎重に「半周回して1/4周戻す」というのを休憩を挟みつつゆっくりやっていきました。
作業中に引っかかったり力を込めるということは全く無く、最後まで軽い力でスムーズに回すことができました。
RD組み付け
作業後、改めてRD側のネジにも焼き付き防止剤を塗布してRD組み付け再挑戦。

タッピング後はRDのネジがするっと入るようになりました(^^)
RDの取り付けにはT25トルクスレンチを使用します。指定の締め付けトルクは10-12Nmです。

ところで、本来であればトルクレンチを使って締め付けトルクを計りながら組み付けたいところですが、私の場合はRDの組み付けだけはこのトルクスレンチを使います。
理由はタップツールと同様にトルクの中心をネジの中心に合わせたいからです。トルクレンチは持ち手が一箇所だけなので、回転方向以外の力が掛かってハンガーを曲げてしまう恐れがあると感じるからです。
RDのデザインを改めて眺める
こちらは完成後のRD部のクローズアップ写真。

なんて美しいデザイン。計算ではなく感性によってフリーハンドで描かれたようにも思える曲線がRDをただの機械ではなく芸術品の域に仕立て上げているように思えます。
つづく。
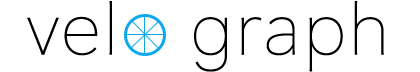














コメントを残す